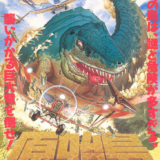1989年、アーケードゲームセンターには熱気が満ちあふれていました。『ダブルドラゴン』や『ファイナルファイト』が人気を博す中、ひときわ異彩を放つ格闘ゲームが登場しました。それが、SNK(当時は新日本企画)による『ストリートスマート(STREET SMART)』です。ベルトスクロール型アクションと対戦格闘の要素を融合した斬新なゲーム性に、プレイヤーたちは釘付けとなりました。
開発背景や技術的な挑戦
『ストリートスマート』は、SNKが1989年にリリースしたアーケードゲームで、同社が格闘ゲームジャンルに本格的に取り組み始めた初期の作品です。当時、格闘アクションゲームといえば『ダブルドラゴン』のようなベルトスクロール型が主流でしたが、『ストリートスマート』は1対1の戦闘にフォーカスを当てることで、後の対戦格闘ゲームの礎となる仕組みを先取りしていました。
本作は横スクロールではなく固定画面での戦いが中心で、攻撃・防御・ジャンプといった操作を用いながら、テンポよく進む格闘アクションを展開。キャラクターごとの個性や連携技の存在も、当時としては珍しい要素でした。2人同時プレイも可能で、協力プレイの後には「グラッジマッチ」と呼ばれる勝負イベントが発生し、報酬の分配をめぐってライバル同士が激突するユニークなシステムが盛り込まれています。
プレイ体験
ゲームはアメリカを舞台にしたストリートファイトを巡る全8ステージ構成で、各地のボスキャラクターたちとのバトルが待ち受けています。プレイヤーは2人のファイター「空手家」と「クラッシャー」から選択でき、それぞれ異なる必殺技を持っています。
アーケードらしい硬派な難易度と、体力の駆け引きを重視したゲームバランスはプレイヤーの闘志を刺激しました。また、敵を倒すことで得られる「報酬」が貯まっていく要素があり、ゲームクリア時に所持金に応じたエンディングが分岐するなど、やり込み要素も用意されていました。
特に印象的だったのは「観客が応援する声」や、倒れた際のリアクションの多彩さといった演出面で、格闘イベントのライブ感をアーケード筐体で再現しようとする工夫が随所に見られました。
初期の評価と現在の再評価
『ストリートスマート』は、発売当時のアーケード業界で一定の注目を集めました。格闘に特化したゲーム性と2人プレイの協力と対立を同居させた独自の構造は、革新的と評価されました。しかしその後、より洗練された『ストリートファイターII』などの登場により、影が薄くなっていきます。
とはいえ現在では、SNKの格闘ゲーム黎明期を代表する作品として再評価されており、『餓狼伝説』や『KOF』シリーズへの道を開いた源流の一つと認識されています。SNKの40周年記念タイトルに収録されるなど、歴史的な価値が見直されています。
他ジャンル・文化への影響
『ストリートスマート』は、固定画面式の格闘対戦というゲームスタイルを1989年という早期に実装していた点で、格闘ゲームというジャンルの形成に影響を与えた先駆的な存在です。SNKの後年の代表作である『餓狼伝説』シリーズの開発思想に通じる部分が多く見られ、特に「1対1の真剣勝負」というコンセプトは本作から始まっているとも言えます。さらに、本作の第1ステージのBGMが、後の『餓狼伝説』において対戦時の楽曲としてリメイクされるなど、SNK内部での文化的継承も見られます。
リメイクでの進化
もし『ストリートスマート』が現代にリメイクされるならば、まず求められるのは操作性と演出の強化でしょう。HDグラフィックによるキャラクターデザインやアニメーションの一新、現代的なコンボシステムやオンライン対戦の導入などが想定されます。また、ストーリーモードを拡張し、各キャラクターに背景や目的を持たせることで、ドラマ性を高めることも可能です。さらに、格闘大会形式の大会モードや、観客のリアクション演出を強化したライブバトル感の強調なども、リメイクにおける魅力となるでしょう。
まとめ
『ストリートスマート』は、格闘ゲームというジャンルが形を成す前夜に登場した、革新的なアーケード作品でした。1対1の対戦要素、協力プレイ中の裏切り、報酬によるエンディング分岐といった独自の試みは、後の格闘ゲームに少なからず影響を与えています。現在の視点から見れば、まだ未完成な部分も多かったかもしれませんが、SNKというメーカーがどのようにして格闘ゲームの世界に足を踏み入れていったのかを知る上で、非常に価値のある一作です。再評価が進む今、改めてこの作品を振り返る意義は大きいといえるでしょう。
© 1989 SNK CORPORATION